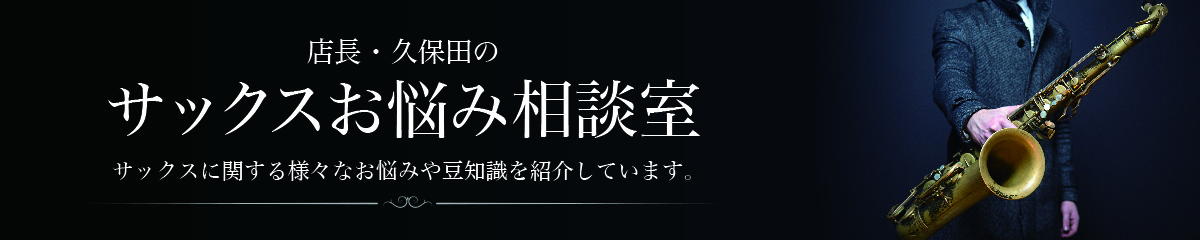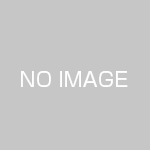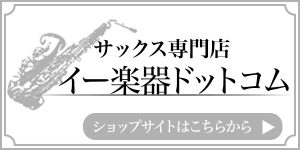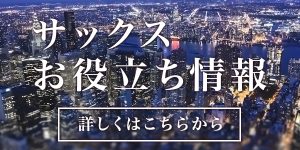サックスがどのくらいの数の部品から出来ているかご存知ですか?一般的なアルトサックスで、約600点の部品から構成されています。その膨大な数の部品が、溶接やら、はんだ付けやら、ネジ留めやらの色々な方法で、ひとつのサックスに組み立てられている訳です。その方法の中で、「サックスはこれで組み立てられている」と言っても過言ではないのが、「はんだ付け」です。今日はちょっとディープな、サックスのはんだ付けの世界を紹介します。
サックスがどのくらいの数の部品から出来ているかご存知ですか?一般的なアルトサックスで、約600点の部品から構成されています。その膨大な数の部品が、溶接やら、はんだ付けやら、ネジ留めやらの色々な方法で、ひとつのサックスに組み立てられている訳です。その方法の中で、「サックスはこれで組み立てられている」と言っても過言ではないのが、「はんだ付け」です。今日はちょっとディープな、サックスのはんだ付けの世界を紹介します。
ラジオやオーディオアンプ等の、電子機器の製作を趣味としている方々は、熱したはんだごてと糸はんだで配線を結合します。電子製品の中にあるプリント基板の裏側の金属の 「点々」は、はんだ付けのはんだで基盤の回路と部品が接着された部分です。はんだは鉛とスズの合金で、電気配線用のはんだはスズ60%:鉛40%で、180℃前後で溶け、固まり方も速いです。それに対し金属接着用のはんだはスズ50%:鉛50%とスズの比率を落とし、融点も高く、ゆっくり固まるようにしてあり、はんだをしっかり盛るのに適しています。また固まった後も柔軟性があり、金属が収縮してもはんだ付け部分が割れ難いという特性があります。はんだとともにサックスの組み立てに使われるのが「銀ロウ」です。銀35%:銅35%:亜鉛30%前後の配合比率の合金で、700℃前後で溶け出します。アルミニウムやマグネシウム以外のほとんどの金属に使用可能で、伸びがよく、強度にも優れた汎用性の高い接合材です。銀ロウはかなりの高温で接着しているので、取れる事はほとんどありません。比べて、パンダ付けは溶ける温度が銀ロウより低いため耐久性は劣りますが、修理がし易いというメリットがあります。
 このように融点(溶ける温度)の違う合金を使うのには、サックスの組み立てと修理を考えた、合理的な理由があります。多くの部品を結合して組み立てるサックスでは、三つ以上の部品を熱接合する場面が多くあります。一種類のはんだだけで接合していたら、「一か所を接合した後、他の場所を接合していたら、その熱が伝わって前の部品が溶けて落ちた」、なんて事に成りかねないのです。また楽器の使用中の部品への力の加わり方、それによる修理や調整の確率の高い場所、振動を伝えるべき場所とそうでない場所、等々。サックスの製造に携わる技術者たちは、接合の温度差という凄く細かい事にも配慮しているのです。
このように融点(溶ける温度)の違う合金を使うのには、サックスの組み立てと修理を考えた、合理的な理由があります。多くの部品を結合して組み立てるサックスでは、三つ以上の部品を熱接合する場面が多くあります。一種類のはんだだけで接合していたら、「一か所を接合した後、他の場所を接合していたら、その熱が伝わって前の部品が溶けて落ちた」、なんて事に成りかねないのです。また楽器の使用中の部品への力の加わり方、それによる修理や調整の確率の高い場所、振動を伝えるべき場所とそうでない場所、等々。サックスの製造に携わる技術者たちは、接合の温度差という凄く細かい事にも配慮しているのです。
アメリカンセルマーのU字管ははんだ付けしてあるので有名です。管体を伝達する音のロスが少ないとの評価ですが、現代の楽器に取り入れられたという話は聞いたことはありません。コスト対効果の問題でしょうか。現代の楽器には化学系の「接着剤」が多用されているそうです。はんだや銀ロウに匹敵する性能があるようですが、修理は…困難だと思います。最強強度の「溶接」も近代設備では比較的容易に出来るようです。ロボットアームで高電圧を使ったスポット溶接、なんていうのも出来ちゃうらしいです。でも多くのリペアマンが、「昔ながらのロウ付けとはんだ付けが一番修理し易い」、とおっしゃってます。
——————————————————————————————–
『イー楽器のお得情報』