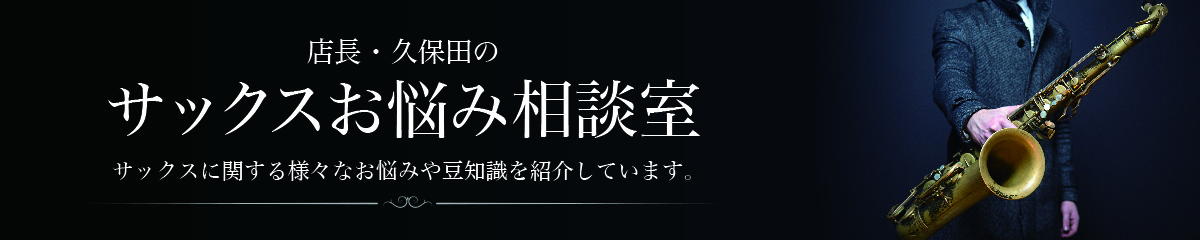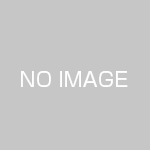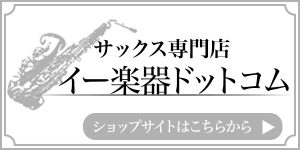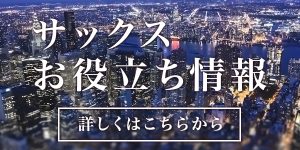ご存知のようにサックスは木管楽器です。
ケーンという天然の植物から作った、リードと呼ばれる「薄い板」を振動させて音を出す構造から、木管楽器の範疇となっています。
木管楽器にはサックスのほか、ほぼ同じ発音構造ですが運指が異なるクラリネット、「ダブルリード」と呼ばれる2枚重ねのリードを使うオーボエやファゴット、またもともと木で出来ていたフルートやピッコロ等があります。
この木管楽器に対し、金属製のカップの中で奏者が自分の唇をふるわせて音を出す、金管楽器があります。ジャズのビッグバンドやブラスバンド、またどんなバンドにでも「金管奏者」の仲間は少なくありません。
今日はそんな、友人たちの金管楽器について考えてみましょう。

サックス等木管楽器は、「管体の穴の位置を切り替えて、出る音の高さをコントロールする」のが音の高さ調整の基本的構造です。
これに対し金管楽器は、「管体の長さを変え、かつ唇で基音を変える」というのが音の高さ調整の仕組みです。金管楽器のトランペットやトロンボーンでは一切楽器を操作せずに、口だけでド、ソ、ド、ミ、ドの音を出すことが出来ます。これは楽器の倍音構造と言い、同じ長さの管でも、唇を調整することだけで出すことが出来るのです。しかしこれだけでは吹ける曲が限られてしまいます。というか、ほとんど無いです。なのでドとソの間、ソとドの間を、管の長さを変える事で出すのです。
トランペットには3本のピストンが付いており、それぞれを押すことで管体全体の長さが変わります。
各シリンダーに追加の管が接続されており、ピストンを押すことで管が長くなります。ざくっと説明すると、1番ピストンは全音、2番ピストンは半音、3番ピストンは一音半だけ音が下がります。そのピストン操作の組み合わせで平均律の12音全部を数オクターブに渡って出すことが出来るのです。1番ピストンと3番ピストンに連結された管は、通常スライド構造を持っており、演奏中に位置の高さを微調整することが出来ます。
トロンボーンも同じような構造で、音の高さ調整はスライドの長さでおこないます。また金管楽器は唇を「ぶるぶる」して音を出しますので、どうしても奏者の唾が管体の中に大量に入っていきます。
サックスの場合、管体内に溜まる水分は、ほとんどが息の水蒸気が冷えて水になったものですが、金管楽器の中に溜まる「唾」の比率は結構高いです。そのぶん、演奏中も頻繁に「唾抜き」をします。
サックスは音を出す振動の源泉がリードですが、金管楽器は奏者の唇そのものです。音が出ている間中、その奏者の唇はもの凄い速さで振動しています。大きな音では大きく震え、小さな音では小刻みに「ぶるぶる」しています。
是非休憩には寛容に付き合ってあげてください。
今週の新着情報
ミュージシャンや理学療法士等、様々なジャンルの専門知識が集結されたサックスストラップ
⇒VANDOREN バンドレン ユニバーサルハーネス サックスストラップ 取扱開始!
ヤナギサワより「Classic Series」登場!
⇒『ヤナギサワ YANAGISAWA ラバーマウスピース Classic Series』取扱開始!
スペインより、調整可能な高級リングリガチャー登場!
⇒『I.M.(インベスティゲーションズ・マンチェガス) リガチャー』
残り28名様 新春お年玉キャンペーン
AIZENスペシャル特典プレゼントキャンペーン開催中
詳しくはこちら