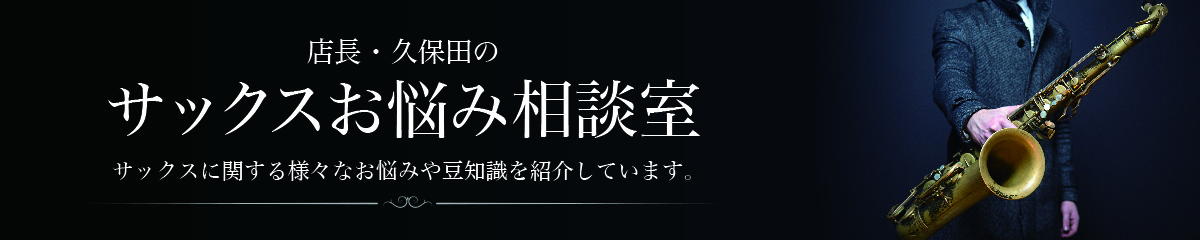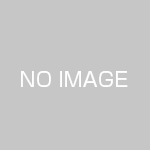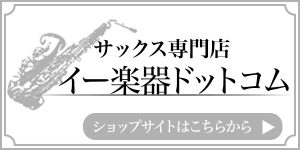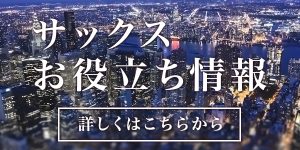サックスという楽器は、個体による個性が大きい楽器です。同じメーカーの同じモデルでも、かつそれが非常に近い製造番号(同時期に製造したもの)だとしても、やはり吹いてみると何らかの違いを感じます。また調整の状態によってもサックスの個性は変わります。パッドの開きが数ミリ変わっただけで音程が上下します。そういった気難しい(?)サックスとの付き合い方のうち、重要なポイントの一つである「音程の癖の見つけ方」についてお話しします。
サックスという楽器は、個体による個性が大きい楽器です。同じメーカーの同じモデルでも、かつそれが非常に近い製造番号(同時期に製造したもの)だとしても、やはり吹いてみると何らかの違いを感じます。また調整の状態によってもサックスの個性は変わります。パッドの開きが数ミリ変わっただけで音程が上下します。そういった気難しい(?)サックスとの付き合い方のうち、重要なポイントの一つである「音程の癖の見つけ方」についてお話しします。
前回はスケールの癖についてお話ししましたが、音楽はスケールの音の並び方のみでは成り立たないので、「フレーズ」や「音の跳躍」も計算に入れる必要があります。そしてこの場合は「楽器の癖」に「奏者の癖」が付加され、かなりややこしい「複合癖」となります。でもそんなに恐れることはありません。少なくとも音程には「正解」があります。(正確には。正解に近い答え、ですが。)なので、自分の演奏に対する、ガイドを用意すればよいのです。
具体的には、皆さんが練習で使用しているエチュード(練習曲)、もしくは正しくマスターしたい旋律(多くの場合は楽曲の主メロディですね)をDTPソフトによる打ち込み(コンピューターへの入力)や、キーボード・ピアノによる演奏で録音します。練習にピアニストに付き合ってもらう、という贅沢な方法も有りですね。要は、正しい音程を確認しながら、自分でサックスで再現していく、という練習をしてみましょう、ということです。楽器自身のスケールの癖はもちろんですが、低音域から高音域に跳躍するときの自分のアンブシャの癖によって、跳躍後の音程が「下がり気味になる」、とか、逆に唇を締めすぎて、「上がり気味になる」場合もあります。こういった演奏上の「傾向」は、ガイド音と比べながら確認していくのが唯一の「矯正方法」です。チューナーを使って音程を一音一音確認しても、フレーズとなると、その傾向は異なって音に出てきます。
 もちろんすべてのレパートリーで、基準音源と自分のサックス演奏を比較するのは大変です。何パターンかの基準音源との練習を重ね、その中でも「自分の奏法を矯正するのに最適なフレーズ」を見つけ出し、定期的にそれと「合奏」することで、自分の奏法の乱れを確認、かつ訂正するのが良いと思います。
もちろんすべてのレパートリーで、基準音源と自分のサックス演奏を比較するのは大変です。何パターンかの基準音源との練習を重ね、その中でも「自分の奏法を矯正するのに最適なフレーズ」を見つけ出し、定期的にそれと「合奏」することで、自分の奏法の乱れを確認、かつ訂正するのが良いと思います。
残り4名様 AIZENより夏の大感謝祭!
スペシャル4大特典プレゼントキャンペーン開催中
詳しくはこちら
- ホーム
- サックス 本体, サックス 練習・レッスン
- 自分の楽器の奏法を探す